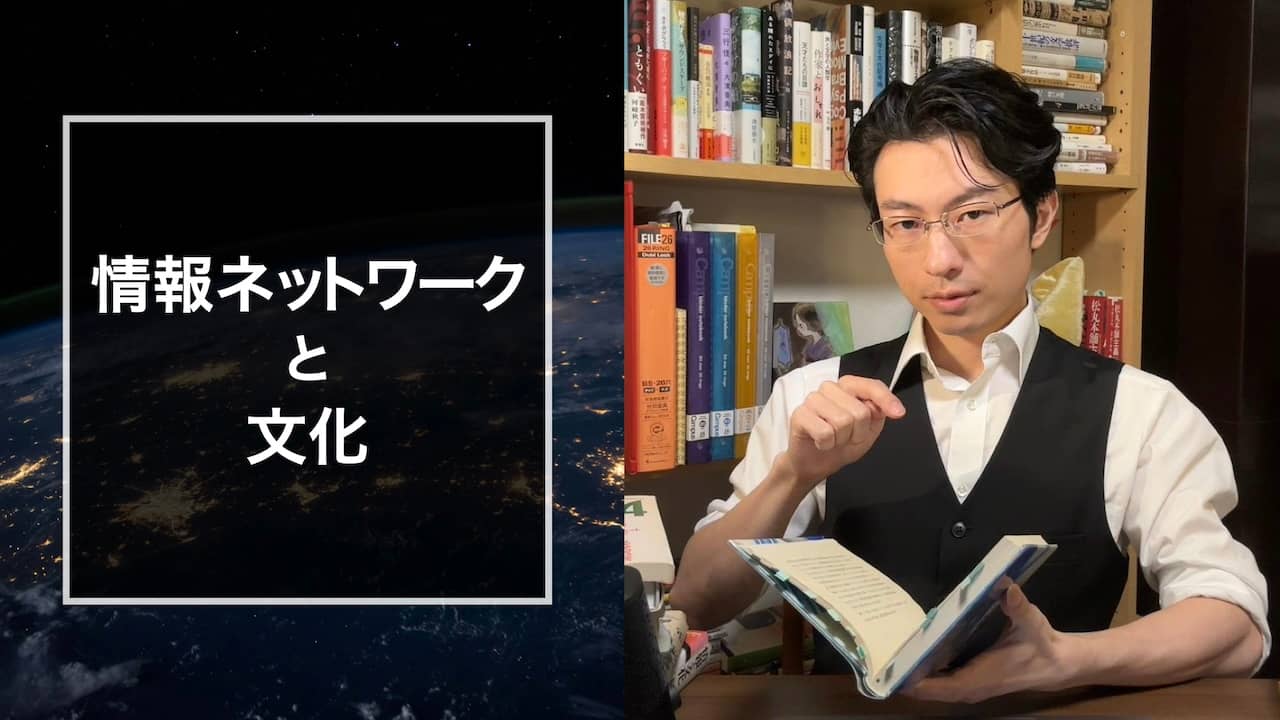現代の生活に欠かせない、インターネットと電子端末。
しかしそれらは、人類にとってどのような存在なのか。
社会に普及しあまりに当たり前なものとなってしまったために、あらためて説明するには困難が伴います。
今回は特別編、特定の書籍ではなく「情報ネットワークと文化」というテーマに沿って、80年代〜90年代の情報論の傑作たちを解説しながら、
これからの私たちはどのように情報環境を生きていけばいいのか、詩人・吉増剛造の詩や、中島敦の短篇小説「悟浄出世」「悟浄歎異」の読解を踏まえて考察します。
動画の目次
1:80年代の情報論
2:90年代の情報論
3:この世界との接触
オンラインでもオフラインでも活動を続ける彗星読書倶楽部は、2025年7月のサービスリニューアルに際し、電子空間上で書物を読む・書く・語ることの意味を明確にするため、情報論・メディア論を扱う必要に気づきました。
現在の私たちの状況をなるべく客観的に捉えるために重要なのは、発表から時間が経過した言説を探り、かつて想像された未来と、実際に到来した未来である現在を比べてみることです。
そこで、21世紀に入る前の書籍を読み解いてみましょう。40年前の言葉にしか見出しえない思考の可能性に、今だからこそ気付けるかもしれません。
今回の動画では、
80年代の名著として、批評家・粉川哲夫『情報資本主義批判』と産業組織論の専門家・今井賢一『情報ネットワーク社会』を取り上げ、まだ「情報ネットワーク」「高度情報社会」の具体的な姿が浮かびづらかった時期の想像力を確認します。
90年代からは、雑誌『現代思想』1996年4月号に掲載された、情報学者・西垣通と美学者・吉岡洋の対談を読み解きながら、そこに哲学者・森岡正博の傑作『意識通信』を並べ、当時の「通信」の冷静な分析を通して出現する──出現してしまう、人間のナマの部分に出会います。
最後に、私たちはこのあとの世界でいかに生きればいいか、いかに情報ネットワークを利用すればいいかを考えます。
人間がメディアを利用する理由が「世界との新しい接触」を望むからだとすると、それと引き換えに、私たちは間接化と合目的性にとらわれているとも言えます。
そんな状況で、私たちは満足のいく文化を作り出せるでしょうか?
ヒントを吉増剛造と中島敦に求め、この迷宮から逃れる方法を探りましょう。
夏のシーツに、素肌に
都市全体が落雷となって集中する
(吉増剛造「渋谷で夜明けまで」)
最後に、森 大那が提案する「世界との新しい接触」の方法が語られます。
2025年9月現在、もっとも長い解説動画です。